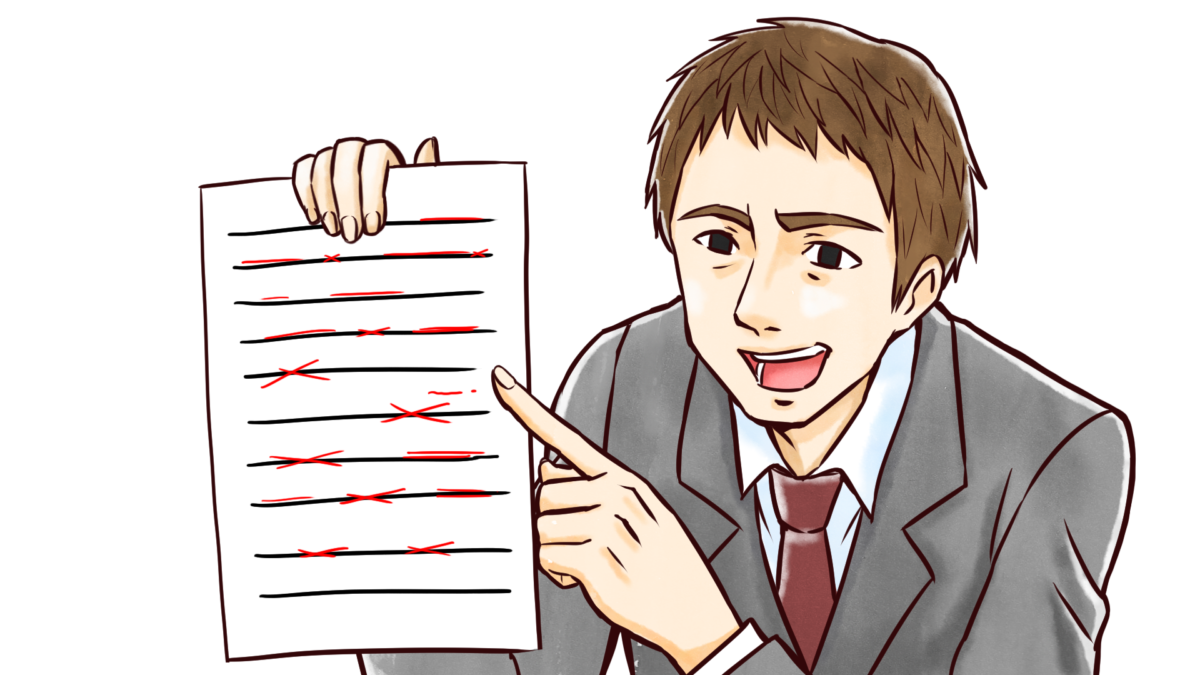お金を貸すとき、一体貨したお金にどれだけ利息をつけられるのか。
本記事では、貸付金に対する上限金利を法律的な側面から解説します。
上限金利は15~20%です
お金を貸し付ける際の上限金利は、利息制限法によって定められています。
利息の上限は貸付金の額によって変わります。具体的な上限利息は以下。
・貸付元本の額が10万円未満の場合は年20%
・貸付元本の額が10万円以上100万円未満の場合は年18%
・貸付元本の額が100万円以上の場合は年15%
※利息制限法第1条
つまり、上限利息の幅は15~20%ということになります。
これを超える利息は利息制限法に違反することになります。
個人間の貸し借りなら利息制限法に抵触しても刑事罰を課されることはありませんが、利息制限法の上限金利を超える部分は無効となりますので、絶対に15~20%の範囲で利息を設定するようにしてください。
名目を変えてもだめ
表面上の利息は利息制限法の範囲内でも、礼金、割引金、手数料、調査料などの名目で利息とは別にお金を請求している場合、これは利息とみなされます。
例えば、人に50万円を貸し付けた場合の利息を18%で設定したとして、手数料という名目で別途月々500円を徴収していたら、これは利息に当たります。
50万円の貸付で月500円なら、年利にすれば1.2%。利息が18%なら、合計して19.2%の利息になってしまうので、これは利息制限法上アウトです。
第三条 (みなし利息)
前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
遅延損害金の上限金利は?
遅延損害金とは、債務者が返済を怠った場合に追加で課されるペナルティ的な金利のことを指します。
ではこの遅延損害金の上限金利はどれくらいか。これも利息制限法によって定められています。
第四条 (賠償額の予定の制限)
金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
利息制限法第4条では、遅延損害金の上限は1.46%。このパーセンテージを超える部分は無効となります。
すなわち、貸付元本が10万円以下で利息を上限の20%に設定している場合、遅延損害金の上限金利は29.2%になります。
ただ、利息制限法第7条では、「賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。」とあるので、実質的に利息と合わせて遅延損害金を合わせた上限は20%となります。
1.46%を超える遅延損害金の設定は、超えた部分は無効となるのでご注意ください。
おわりに
闇金では、トイチ(10日で1割の利息)、トゴ(10日で5割の利息)、ヒサン(1日で3割の利息)などの、法外すぎる金利を請求する慣習がありますが、もちろんこれは利息制限法にゴリゴリに違反しています。
お金を借りるとき、あるいはお金を貸すときは必ず利息制限法の原則を思い出し、適正金利で取引するようにしてください。