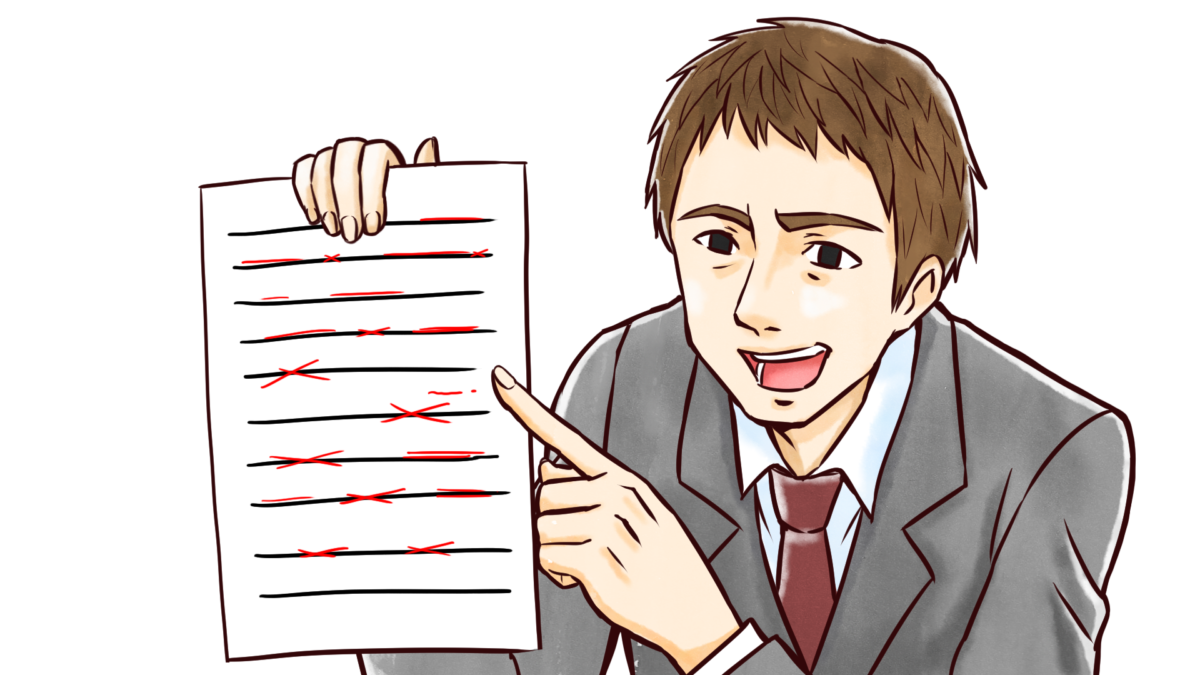借地借家法は賃借人(借り手)を強く保護しているため、賃貸人(貸し手)が賃貸借契約の更新拒絶するには、正当事由が必要となり、よっぽどのことがないと契約の更新を拒むことができません。
本記事では、賃貸借契約の更新を拒否する正当事由とは何なのかという点について解説します。
賃貸借契約の更新拒絶の要件について
賃貸借契約の更新は、期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をすることで更新を拒否することができます。通知を行わない場合は、従来通りの契約で更新されたものとみなされます(借地借家法第26条1項)。
つまり、賃貸人が更新を拒絶したければ、一年前から六月前の間に更新しない旨の通知をする必要あり。
しかし、冒頭でも書いたとおり、居住権は人が生きていく上で非常に重要な権利であり、それを簡単に奪うことはできません。
借地借家法は法的弱者である賃借人保護が目的のため、賃貸人が賃貸借契約の更新を拒否する場合、正当事由が必要となります。
更新拒絶の正当事由(借地借家法28条)
賃貸人からの更新拒絶あるいは、解約申し入れに必要な正当事由が以下。
・ 建物を自己使用する必要があるとき(単なる経営上の都合は考慮されない)
・ 建物老朽化等に伴い建て替えの必要があり、立退料などを払う場合(あくまで考慮されるのみで、立退料を払ったからといって必ず更新拒絶できるわけではない)
・ 信頼関係が破壊されている場合(家賃を滞納している、騒音がひどい、無断でペットを飼ってるなど)
上記であげた正当事由は借地借家法第28条で定められているものですが、これはあくまで判断基準にすぎず、総合的に状況を考慮して正当事由の有無を判断することになります。
実務的には、家賃滞納などの信頼関係破壊が更新拒絶のキー
実務的には、信頼関係が破壊されたことが更新拒絶の要件になることが多いでしょう。
例えば賃借人の家賃の滞納。
一ヶ月程度ならまだしも、こちらが何度催促しても家賃を納めず半年以上滞納し続けるなどは、双方の信頼関係が破壊されたとして、更新拒絶の正当事由になり得るでしょう。
具体例を出すと、神戸地裁の建物明渡等請求事件(平成28年12月8日判決)。
本事件は、神戸市から建物を借りて文化交流施設を運営していた賃借人の度重なる家賃滞納が争点となった裁判です。
賃借人は資金計画の甘さと財務状況の悪化から家賃滞納が常態化し、神戸市側がブチギレ。
神戸市側は、賃貸借契約の更新を拒絶し、立退料なしで建物を開け渡すことを請求します。
ここで争点となったのが更新拒絶の正当事由。
賃借人は、平成18年2月~3月分の家賃を100日遅滞(41万9925円) 。
また、平成18年4月~9月分の家賃を176日遅滞(209万9628円) 。
(上記はあくまで一例。上記以外の期間も度重なる家賃滞納あり)
こうした家賃滞納が常態化した結果、裁判所は更新拒絶の正当事由を認め、神戸市側の勝訴につながりました。
参考: https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/086488_hanrei.pdf
実際に賃貸人側が更新拒絶をする場合は、こうした判例を頼りに更新拒絶をするかどうかを決めるといいでしょう。
おわりに
借地借家法は賃借人保護が強い法律なので、トラブルが多い賃借人を追い出したいと思っても、追い出すための要件を充足させることは容易ではありません。
借地借家法で定める更新拒絶は強行規定なので、更新拒絶を正当化する契約条項を盛り込んでもそれは無効となります。
賃貸借契約でトラブルが発生したら弁護士さんに相談するのが一番でしょう。
当事務所は行政書士事務所なので、契約書作成だけはお手伝いできるので、賃貸借契約書を作成する際にはぜひお声がけいただければと思います。
私個人の考えを述べると、借地借家法は賃借人保護が強すぎて、賃貸人にとってはかなり不利。
契約の原則論で言えば、賃借人が定められた債務を履行しない(家賃を払わない)のであれば、その時点で契約解除が可能になるのが筋ではないかと私は思います。
先ほど紹介した神戸地裁の建物明渡等請求事件も、度重なる家賃滞納があって初めて更新拒絶が可能になったわけですが、もっと早い段階で更新拒絶ができてもいいのにと思ってしまいます。
大家も慈善事業をやっているわけではないので、家賃を払ってもらわなければ、その間その物件からの収入は0。借入金があれば、無収入の中返済をすることになります。
それでも賃借人保護のためにすぐに契約解除できないのは、やはりちょっと酷ではと感じるのですがね・・・
ではでは。