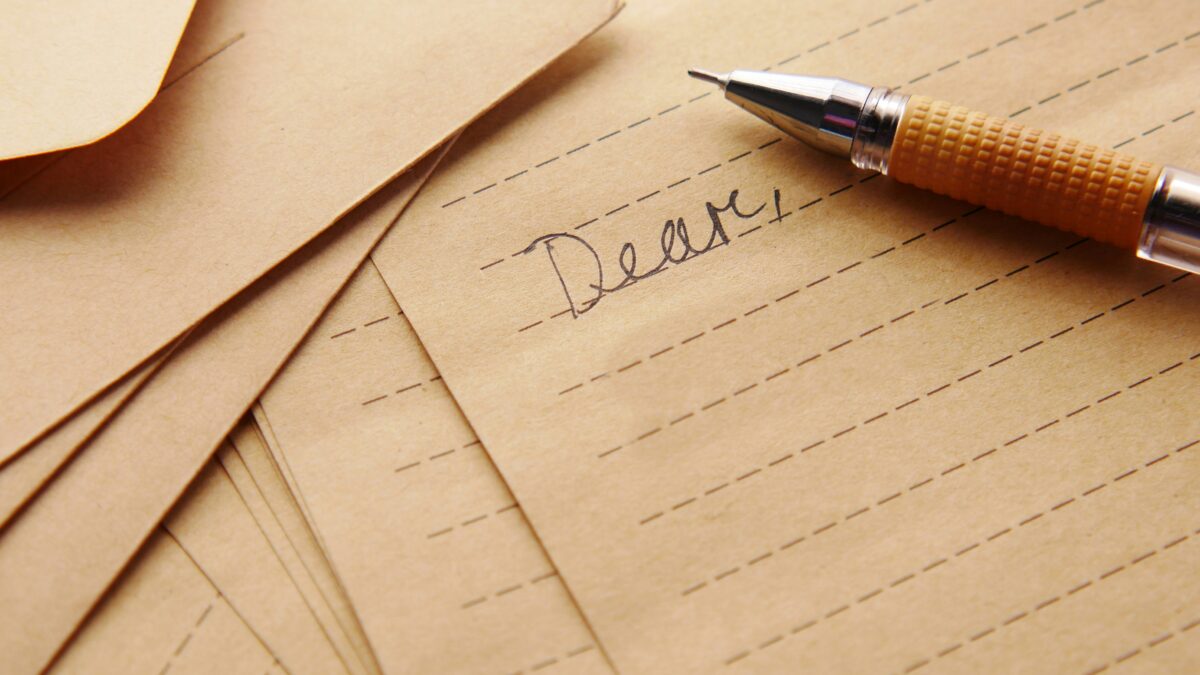「業務委託契約書」「売買契約書」「賃貸借契約書」、契約の種類は多種多様ですが、多くの契約書に共通する一般条項があります。
一般条項を理解しておけば、一般条項は汎用的に使いまわせるので契約書を作る立場になったときにかなり楽になるでしょう。
本記事ではそんな一般条項を紹介します。
一般条項とは?
一般条項に明確な定義はありませんが、本記事では契約書でよく使われる条項と定義しています。
本記事で紹介する一般条項は以下です。
・目的条項
・契約期間を定める条項
・解除条項(中途解約条項)
・秘密保持条項
・反社会的勢力排除条項
・損害賠償条項
・不可抗力条項
・残存条項
・管轄条項
・誠実協議条項
では一つずつ解説していきます。
目的条項
本契約の目的を示す条項が目的条項です。
以下は実際に私が作成したWebライター用の業務委託契約書の目的条項です。
第○条 業務内容
1. 甲は、乙に対して、以下の記事執筆業務(以下「本件業務」という)を委託する。
(1) 甲が運営する会員月刊誌「日本行政」に掲載する原稿の作成
(2) 原稿に使用する写真の撮影や、イラスト(フリー素材等の利用可)等の作成
(3) 原稿作成に付随する、取材やインタビュー等の業務
(4) これらに付随する一切の業務
上記のように業務委託契約書では「業務内容」と書かれている場合もあります。
売買契約だと概ね以下のような目的条項になります。
第○条 契約の目的
本契約は、甲が所有する[商品名](以下「本件商品」という)を、乙が甲から買い受け、甲がこれを乙に売り渡すことに関する基本的な事項を定めることを目的とする。
このように本契約の目的が客観的に理解できるよう記述しておくと、相手方と認識の齟齬が生じにくいため有益です。
契約を結んだあとになって、「そんな契約だとは知らなかった!」と言われてしまっては困りますからね。
加えて、目的条項は紛争になったときにも役立ちます。
なぜなら、目的条項を定めておけば第三者が契約内容を客観的に理解できるため、裁判になっても契約の意図がわかりやすくなるからです。
というわけでほぼ全ての契約に目的条項を定めておくのがマストでしょう。
契約期間を定める条項
ほぼ全ての契約には期限があります。その契約期限を定める条項。
契約で定めた権利や義務がいつまで存続するかを定めておかないと、当事者同士で困惑と負担が生じます。
なので、多くの契約書では契約期限を設定します。
サンプル条項は次のとおり。
第〇条 契約期間
本契約の有効期間は、〇〇年〇月〇日から〇〇年〇月〇日までとする。
なお、賃貸借契約などの更新前提の契約は、次のような自動更新条項が設けられています。
第〇条 自動更新
本契約の期間満了日の1ヶ月前までに、いずれかの当事者から相手方に対し、書面による更新拒絶の意思表示がない場合、本契約は同一条件にて更に2年間更新されるものとし、以後も同様とする。
契約更新が前提の場合、契約期間満了前にいちいち契約更新の有無を確認するのは面倒なので、相手側から何も通知がなければ自動で契約更新するという内容です。
いわゆる自動更新条項。
契約実務を円滑に行う場合、あるいは契約を継続した方がメリットが大きい場合は、盛り込んでおいて損はない条項と言えるでしょう。
解除条項(中途解除も含む)
契約解除を規定する解除条項。こちらもほぼ全ての契約書に設けられている条項です。
解除条項を設けていなくても、一定の条件に当てはまれば民法に基づいて契約解除ができないわけではないですが、契約実務を考えれば、個別に解除条項を設けるのが一般的です。
以下はサンプル解除条項。
第○条 契約解除
1. 甲及び乙は、相手方に1ヶ月前までに書面をもって通知することにより、本契約を解除することができる。なお、甲は、解除により乙に損害が生じた場合でも、その賠償責任を負わない。
2. 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続きを要しないで、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約に定められた条項に違反したとき
(2) 本契約に定められた債務の履行をしないとき、又は債務の履行が困難であることが明らかなとき
(3) 相手方に対する詐術その他背信的行為があったとき
3. 前項の場合、本契約を解除された当事者は、解除した当事者が解除により被った損害の一切を賠償するものとする。
上記のような解除条項を設けておけば、相手方に契約内容の履行を促すようプレッシャーを与えられます。
かつ、一ヶ月前に通知すれば無条件で契約を解除できるので、契約を終了させたいときに終了させられます。
なお、解除条項を設けなかった場合民法の規定に沿って契約解除をすることになります。
第540条 (解除権の行使)
1. 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2. 前項の意思表示は、撤回することができない。
相手が債務を履行しない場合(相手が契約に定められた義務を実行しないこと)、は催告することで解除することが認められています。
第541条 (催告による解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
例えば車の売買契約で、買い手が車の代金を払わなかったら困ってしまいます。
そこで民法では上記の「催告による解除」を認めており、相手に催告することで契約解除が可能になるのです。
なお、催告によらない解除も法定されており、要件に合致すれば催告することなく契約を解除させることができます。
長くなるので詳しくは当サイトの以下記事を参照。
参考: 【契約実務】無催告解除の要件と契約書に定めておくべき解除事由
秘密保持条項
契約内容を無関係の人間にぺらぺら喋られたら重要機密が漏洩し、多大なる損失を被る可能性があります。
そこで、契約内容の秘密を守るために、秘密保持条項を設けておくのです。
以下は秘密保持のサンプル条項。
1. 甲及び乙は、本契約の遂行により知り得た業務上の情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的には使用してはならない。
ただし、弁護士、公認会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負うものに対して当該情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、本項条文と同内容の義務を負わせることを条件として、自己の責任において必要最小限の範囲において当該情報をそれらの者に対して開示することができる。
また、法令に基づき行政機関及び裁判所から当該情報の開示を求められた場合においても、自己の責任において必要最小限度の範囲に限って開示することができる。
2. 前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しない
(1) 相手方から開示を受けたとき既に自己が保有していた情報
(2) 相手方から開示を受けたとき既に公知となっている情報
(3) 相手方から開示を受けた後に自己の責めによらず公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
原則、情報は勝手に開示してはだめで、一定の条件のもと開示を許可するという立て付けです。
多くの契約書がこのフォーマットかと思います。
全ての契約内容を秘密保持の対象にすると実務に差し障りがある場合は、特定の情報だけに限定して秘密保持契約を結ぶという手もあります。
契約内容によってそこは臨機応変に対応しましょう。
反社会的勢力排除条項
契約相手が反社会的勢力だと思わぬ不利益が発生します。
そこで多くの契約書でほぼテンプレ的に反社会的勢力を排除する条項を設けています。
サンプル条項は以下。
第〇条 反社会的勢力
本契約の当事者は、それぞれ相手方に対し、次の各号に掲げる事項を表明し、保証する。
(1) 自己、その役員(取締役、執行役、代表者、業務執行社員その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)及び従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
(2) 反社会的勢力と関係を有しないこと。
(3) 反社会的勢力に対し、資金提供、便宜供与その他いかなる利益供与も行わないこと。
(4) 自ら又は第三者をして、暴力的行為、脅迫的行為、詐欺的行為その他の違法行為を行わないこと。
そして、追加的に、相手が反社会的勢力であった場合契約解除をできる旨を設定している条項を設ける場合もあります。
サンプル条文を読めば分かるとおり、暴力団(いわゆるヤクザ)だけでなく、暴力団に準ずる者(例えば半グレなど)も排除の対象にしています。
安全な経済活動をするためにも、反社排除条項はマストでしょう。
損害賠償条項
契約相手の契約違反や、予期せぬ事故などで損害が発生したときのために、損害賠償を定めるのが損害賠償条項です。
損害賠償条項はあらゆるパターンが想定されるのでテンプレ条項を使い回すのではなく、契約内容によって条項を決める必要があります。ポイントは以下。
損害賠償条項のポイント
損害賠償の範囲: どのような損害が賠償の対象となるのかを明確に定める必要があります。通常損害(通常生じる損害)だけでなく、特別損害(予見可能性のある損害)も賠償の対象とするか否かを検討しましょう。
損害賠償額の算定方法: 損害賠償額を具体的に算定する方法を定めることが望ましいです。例えば、売上減少額や修繕費用などを基準とする、あるいは一定の金額を定めるなどが考えられます。
責任制限: 損害賠償額に上限を設けたり、特定の損害については賠償責任を免除したりする場合があります。責任制限を設ける場合は、その範囲や条件を明確に定める必要があります。
免責事由: 天災や不可抗力など、当事者の責めに帰すべからざる事由によって損害が発生した場合、賠償責任を免除する規定を設けることがあります。
損害賠償額は上限値を設定しておくのが望ましいので、次のような条項が考えられます。
第○条 (損害賠償)
1. 甲及び乙は、本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、相手方に対して、損害賠償請求をすることができる。
2. 前項の各当事者が負う責任は、金○○円を上限とする。ただし、損害賠償を負う当事者の故意または重過失がある場合は、この限りではない。
原則は上限を設定しておき、相手方に故意や重過失があった場合のみ上限を撤廃するという、わりとよくある損害賠償条項です。
不可抗力条項
損害が発生した場合は、損害を負わせた当事者はその損害を埋め合わせる義務を負います。
とはいえ、損害を負わせた側にも止むを得ない事情がある場合もあります。
例えば、荷物をある地点まで運ぶ運送契約を結んだものの、大地震の発生によって、期限内に荷物を運べなかったとします。
地震という予測不可能な天災にまで、損害を負わせるのはさすがにかわいそうなので、そうした不可抗力的事由は免除するのが不可抗力条項です。
サンプル条項は以下。
第○条 不可抗力免責
天変地異、戦争・内乱・暴動、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキ等の争議行為、その他不可抗力による本契約に基づく債務の履行遅滞又は履行不能が生じた場合は、いずれの当事者もその責任を負わない。ただし、金銭債務を除く。
金銭債務を除いてるのは、民法419条3項の考えに基づいています。
というのも、金銭債務は外部からの借入等などの方法により返済可能であり、不可抗力で返済できなくなる事由がほぼ発生しないからです。
特約で金銭債務を不可抗力免責の対象にしても構いませんが、あまり一般的ではありません。
残存条項
残存条項(または存続条項)とは、契約終了後も一定の条項の効力を存続させるための規定です。
通常、契約は有効期間の満了や解除などによって終了すると、その効力はすべて失われるのが原則です。しかし、契約の内容によっては、契約終了後も一定の義務や権利関係を維持する必要がある場合があります。
主に機密保持契約などで使われることが多いです。
サンプル条項は以下。
第○条 残存条項
本契約終了後も、甲及び乙は、本契約期間中に知り得た相手方の秘密情報を第三者に開示してはならない。
残存条項は必須ではないですが、契約内容によっては定めておかないと思わぬ不利益が発生しますので、必ず確認するようにしてください。
合意管轄条項
管轄とは、契約当事者間で民事裁判を行う場合、どこの裁判所で行うかのことです。
管轄には、「法定管轄」、「指定管轄」、「応訴管轄」、「合意管轄」の4つがあります。
合意管轄とは、あらかじめどこの裁判所で裁判をするかを決めておくというものです。
例えば法定管轄だと、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所に認められるため、場合によっては自分の住所地から遠い裁判所で裁判をする羽目になります。
そうした事態を避けるために、あらかじめ自分の住所地に近い場所に管轄を決めておくのです。
サンプル条項は以下。
第○条 合意管轄
本契約に関する一切の紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
合意管轄条項も大体の契約書に設けられている代表的な一般条項でしょう。
誠実協議条項
何か問題が発生したらお互い誠実に話し合って解決しましょうね、というのが誠実協議条項です。
法律的に設ける意味はないですが、ビジネスマナー的な意味合いで多くの契約書に盛り込まれています。
以下はサンプル条項。
第○条 協議解決
本契約に定めのない事項及び本契約の内容の解釈に疑義が生じた事項については、両当事者間で誠実に協議のうえ、これを解決するものとする。
設けても設けなくてもいいですが、私は儀礼的な意味も含めて設けています。
しかし、繰り返しになりますが法的には特に意味はありません。
おわりに
契約書をよく読むと、本記事で紹介した一般条項がふんだんに使われていることがよくわかるかと思います。
逆に言えば、ここで紹介した代表的な一般条項を全てマスターすれば、契約書を作成するのはそんなに難しくありません。
契約実務に関わる人はぜひマスターしていただければと思います。