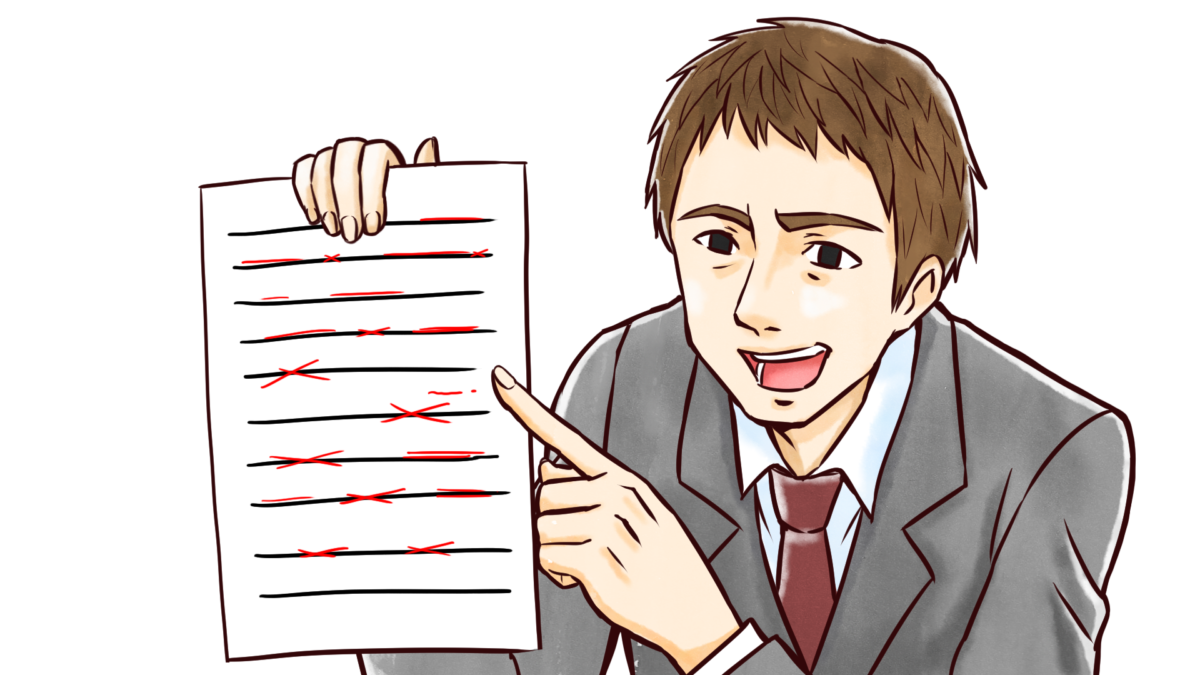知り合いの女性が業務委託契約していたメンズエステを辞める際、高額な違約金を請求されて困ったと相談されたことがあります。
確かに契約書には契約解除をする場合の違約金が定められており、その女性も「契約書に書いてあるから仕方ない・・・」と諦めていました。
今回はこの契約書に定められた高額の違約金の条項は有効なのか、という点について論じていきましょう。
違約金は損害賠償の性質を持つ
大前提、契約自由の原則があるので、相手が契約不履行をした際の違約金を定める旨の条項は何ら問題ありません。
今回の論点はその違約金の額について。
まず、違約金は「違約罰」と書いてない限り、法律上は損害賠償だとみなされます(民法420条)。
損害賠償とは、契約当事者の故意や過失で相手に損害が発生した場合、その損害を賠償することを指します。なので、基本的に、違約金の適正額は損害額だと考えられます。
例えば、契約当事者の契約不履行で損害が10万円発生するなら、違約金の額も10万円が望ましいということです。
さて、では損害額を超えた高額な違約金を定めた場合どうなるのか。
例えば、冒頭で紹介したメンズエステで働く女性のように、「契約解除をしたら違約金100万円」、というような、常識で考えても高額すぎる違約金は認められるのでしょうか。
結論からいうと、高額な違約金は認められない可能性が高いです。
まず、損害賠償の観点からいえば、お店側が100万円の違約金を請求するなら、その女性が契約を解除することで店側に100万円の損害が発生することを証明しなければなりません。
100万円の損害が発生したことを合理的かつ客観的に証明することができた場合、100万円という高額の違約金も正当性を帯びますが、できなかった場合、実際に発生した損害額程度に違約金を減額させられます。
以上の損害賠償の性質から、損害額を超える違約金の定めは無効、あるいは損害額に減額される可能性が高いという結論になります。
違約金が制限されるその他の法律
消費者契約法
契約当事者の一方が消費者で、一方が事業者の場合消費者契約法が適用されます。
その場合高額な違約金を請求することはできず、事業者に生ずべき平均的な損害を超える部分の違約金は無効となります(消費者契約法9条1項)。
宅地建物取引業法
宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、違約金等を定める場合、その違約金の額は売買代金の20%を超える額は設定できないとされています(宅地建物取引業法第38条1項)。
20%を超える部分は無効となります(38条2項)。
民法
民法90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と定めており、高額な違約金は民法90条に抵触する可能性があります。
例えば、何の根拠もなく「違約金1億円」と設定した場合、それは公序良俗に反すると判断されても致し方ないでしょう。
違約罰について
違約金は損害賠償の性質を持つと書きましたが、実は「違約罰」は違約金と似てるようで違います。
違約罰は損害額ではなく、契約不履行の際のペナルティ的な性質を持つので、損害額とは性質が異なります。
なので、契約解除をした際には、実際には10万円の損失が出たわけじゃないけど、10万円の違約罰を求めることができます。
「なんだよ、だったら違約金と書かずに違約罰と書けば結局高額な違約金を請求できるってことじゃないか!」と思うかもしれませんがそれは早計です。
確かに違約罰は損害額を根拠にする必要はないですが、だからといって不当に高額な罰金を設定すると、先ほど紹介した民法90条の公序良俗に反して無効になる可能性があります。
第一このような高額の違約罰はトラブルの源泉にしかならないので、裁判を起こされる確率が高まります。
したがって、違約金だろうと違約罰だろうと、なぜその金額なのか、は客観的に説明できるようにしておくべきでしょう。客観的に説明できないと、裁判になった場合圧倒的不利になります。
おわりに
冒頭で紹介したメンズエステの女性は結局高額な違約金を支払う羽目になったそうですが、正しい法知識があれば彼女のようなことにはなりません。
そうした契約書のことでお悩みの方は、ぜひ当行政書士事務所にご相談ください。
(行政書士は法的な紛争トラブルには介入できないので、紛争が予想される内容の場合は弁護士にご相談ください)