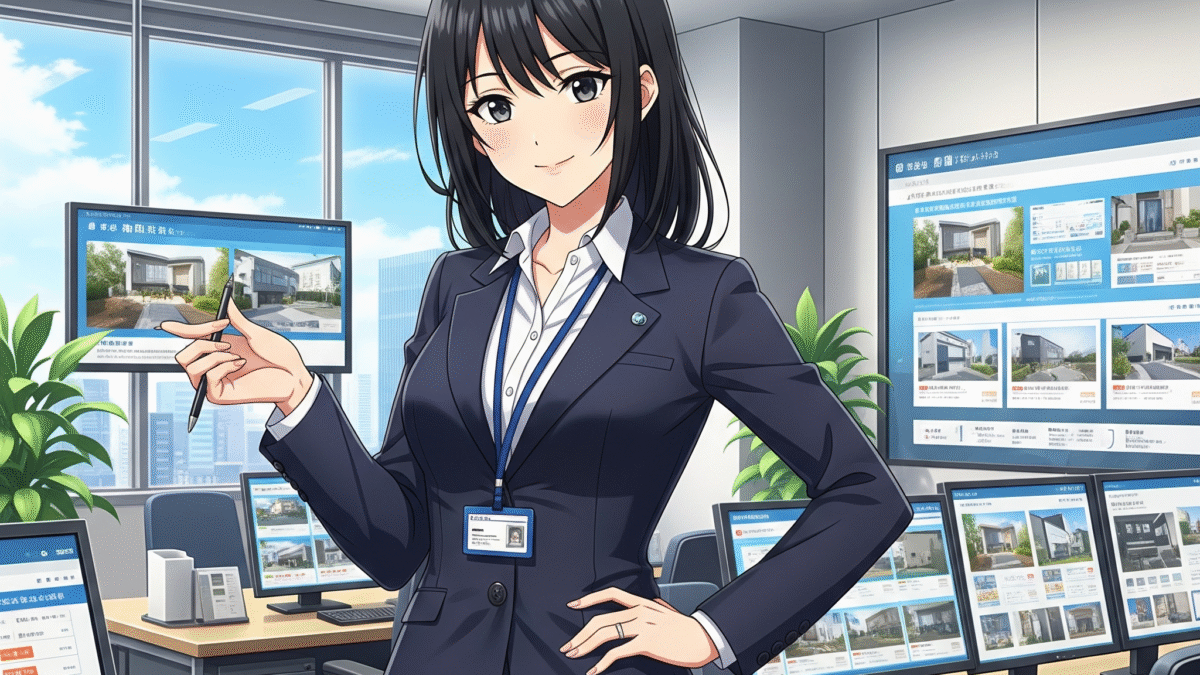物件を人に貸すときに作成するのが不動産賃貸借契約書です。
本記事では、契約書作成専門の行政書士が賃貸借契約書を作成する上でのポイントや注意点などを解説していきます。
ご自身で賃貸借契約書を作成する際の参考になれば幸いです。
賃貸借契約書の作成ポイントや注意点
賃貸借契約書にもいくつか種類がありますが、本記事では一番ポピュラーな、建物を貸し付ける建物賃貸借の解説をします。
なお、重要ポイントに絞って解説するので細かい部分は端折っています(でないとかなりの長文記事になってしまうので)。
まずは物件の特定を
賃貸人として人に物件を貸す場合、まずその物件を契約書面において特定しなければいけません。
物件を特定するには、契約書に物件の以下情報を記載することが望ましいです。
・所在(物件住所)
・家屋番号
・建物の構造
・床面積
不動産会社によっては家屋番号までは書かないことが多いですが、万全な契約書にしたければ書くべきだと私は思います。
家屋番号の調べ方で一番手っ取り早いのが、毎年送付される固定資産税納税通知書で確認する方法。
それ以外だと法務局で登記簿謄本を取得して家屋番号を確認します。
建物の構造は、木造なのか、鉄筋コンクリートなのかを示します。
マンション等を貸す場合は、貸す部屋の階なども特定します。
契約ですから貸し出す物件を正確に特定するのは極めて大事であり、賃貸借契約書の最も肝となる部分です。
賃貸借期間の設定
物件を貸し出す期間を決めます。
通常の賃貸借契約の場合2年が通例となっており、2年を過ぎると更新するという契約が多いです。
賃貸借の期間を定めないこともできますが、その場合賃貸人・賃借人双方がいつでも契約を解除することができます(民法617条)。
長期的な関係を維持した方がお互いにメリットがあるなら、賃貸借期間を設けた方がいいでしょう。
家賃
・賃料の額
・支払い方法
・支払時期
上記の3つを決めます。
ここで大事なのが、銀行振込で賃料を支払ってもらう場合、振込手数料をどちらが負担するかをしっかり明記しておくこと。
「振込手数料くらいどうでもいいでしょw」と言うなかれ。
しっかり明記しておかないと、どっちが振込手数料を負担するか曖昧となりトラブルの火種となります。
それで裁判になったらとても面倒。なので、必ず振込手数料は誰が負担するか明記するようにしてください。
敷金・礼金等の定め
敷金及びに礼金を設定する場合は契約条項に定めておきましょう。
敷金は賃借人が退去する際に、原状回復の費用として充てることができます。
礼金は関東圏での慣習で、家を貸してくれたことに対するお礼のお金という趣旨なので、返還する必要はありません。
敷金・礼金については詳しくは下記参照。
禁止事項
例えば、家を貸す側の視点で考えると勝手にペットを飼われると困ります。
鳴き声がうるさかったり、部屋をめちゃくちゃにされたり、ペットの飼育はマイナス要因が大きいです。
だからこそ、あらかじめ賃借人にしてほしくないことを禁止事項として定めておくのです。
賃貸借契約書において、定番の禁止事項は以下。
・ペット飼育の禁止(あるいは許可した場合のみ可)
・転貸借の禁止(あるいは許可した場合のみ可)
・爆発物、危険物、重量物等の持ち込み禁止
・ギター、ピアノ、ドラム等の楽器を使って演奏の禁止(騒音防止)
珍しいパターンだと、室内でのタバコの禁止を設定する場合もあります。
タバコの禁止を契約で定めることが可能なのかと疑問に思うかもしれませんが、契約自由の原則があるので、公序良俗等に反していない限り当事者同士が合意していれば可能となります。
このように、禁止事項を定めるのは賃貸借に限らず全ての契約において極めて重要となりますので、忘れずに設定しておきましょう。
造作買取請求権の排除
造作買取請求権とは、賃借人が建物に付加した設備等を、賃貸人に買い取ることを請求する権利のことです。
簡単に言えば、賃借人が部屋に取り付けたエアコンや空調設備などを、退去時に、「大家さんこれ買い取ってね」と請求することを言います。
第三十三条 (造作買取請求権)
建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
しかし、造作買取請求権は現代の実情にそぐわないので、通常はこの造作買取請求権排除特約を設けるのが一般的です。
でないと退去時に想定外の出費が発生する可能性があるので、造作買取請求権排除特約条項はマストで設定しておくべき。
私自身も、行政書士として賃貸借契約書の作成を請け負う際、依頼人から特に要求がなくても必ず造作買取請求権排除特約は設定します。
原状回復
賃借人が退去する際、部屋を原状回復して賃貸人に明け渡さなければなりません。
よく勘違いされるのですが、ここで言う原状回復とは、部屋を借りたときと全く同じ状態に戻すことではありません。
通常の使用における物件の劣化や価値の経年劣化等の消耗は、原状回復に含まれず、賃借人の故意、過失等によって物件が損傷した場合などに、現状を回復する義務が発生するのです(民法621条)。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしています。
とはいえ、これはあくまで民法の任意規定の話であり、契約では民法の定めとは異なる規定を設定することも可能です。
私は昔の仕事でよく賃貸物件の契約をしていたのですが、ほとんどの不動産会社が民法621条の原則を排除して、通常損耗も賃借人の原状回復義務にしていました。
実務上、通常損耗を賃借人の原状回復義務にする場合、「通常損耗を含む」などの曖昧な記載では足りず、具体的にどこまでを原状回復の範囲にするかを細かく契約条項に落とし込む必要があります。
原状回復の範囲が曖昧だと、裁判になったとき解釈が分かれてしまい面倒になります。
まとめ
賃貸借契約書を作成する際は、借地借家法及びに民法、さらには消費者契約法など、熟知しておかなければいけない法律がたくさんあります。
作成した賃貸借契約書が消費者契約法に違反していたら問題です。
ご自身で賃貸借契約書を作成する場合は、各法律の趣旨を理解し、当事務所のコラム等などを活用していただき、適法な契約書を作成していただければと思います。